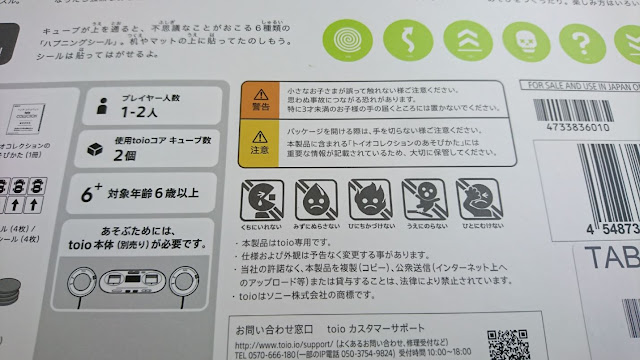電子工作から逃げるな!
逃げるな!とは言え、いきなりDCCコマンドステーションキットを作って失敗しても
私では原因究明が不可能だろうし、失敗が目に見えてるので先日Impressで紹介されていた
「メロディー時計2」と言うキュートなやつからチャレンジ。
記事に「ハンダ付けの解説書と練習基盤もついた電子工作キット」と書いてあったので苦手意識克服に
もってこいな気がした。
先日苦手意識について書いたけど、電子工作もその1つで勉強と言うよりも練習の方が大切な
気もするので出来るだけ数をこなしたい。
メロディー時計2
パッケージからして可愛い、白い基板でパーツが見えてる所がまた良い。
箱にも分かりやすい説明書、ハンダ付けトラの巻、ハンダ付け練習基板の事が書いてある。
必要な工具はすでに揃っているので大丈夫そう。
いつも鉄道模型で使っているものを並べた。
フラックスは基板には使ってはいけないとトラの巻に書いてあったのでいらなかった。
中身、説明書はルビもふってあるので小学生でも出来ると思う。
ハンダ付けトラの巻
これこそ自分に必要なもの。ネットで調べてもたくさん出てくる話だけど練習基板と合わせてしっかり学べる。
温度調節の出来るハンダごてなのでトラの巻に書いてある「ツヤ」が出るように調整した。
くもったり、つのが出来たら駄目と言う事だった。これだけでも楽しい!
練習基板の裏にも色々書いてある、これを10枚くらい練習するだけでも違う気がする。
一応テスターで導通チェックと隣同士つながっていないかもチェック。
メロディー時計2 組み立て
そして本番、リストとにらめっこして不足パーツがないか確認。このセラミックコンデンサだけ絵と形が若干違うけど書いてある数字で確認できる。
説明書にある「あらかじめハンダメッキします」の所をやってそのままパーツを取り付けてしまい
いきなり順番を間違ってしまった。
以後、後で付けるクロックムーブメントと電池ボックスが先についた状態で作業。
まずは抵抗をつけて行く、説明書に「向き・極性」のありなしなどもしっかり書いてあるし
基板にも極性が書いてあるので分かりやすい。
表から足を刺して、折ってからハンダ付け。
トラの巻にある「温め1,2,3」「ハンダ4,5」「6でハンダを離す」「7でハンダごてを離す」
の6と7の間にもう1拍おくと自分の場合うまく流れてくれた。
あまった足はニッパーで切り取り。
どんどんつけて行く、続いて発振子。
セラミックコンデンサ、先に足の長いのから練習できるので良い。
そういえば今回はタイマーを使ってちゃんと撮影してみた。
次はトランジスタ、説明書にどれくらい差し込めば良いか分かる図があるので安心。
基板上にはあからさまに向きが書いてあって間違いようがない。
ごちゃごちゃしてくると基板を安定した状態で置けなくなるけどハンダごてで押さえつけて
熱を伝えつつやると良かった。恐れては行けない。
ブザーは足が短いけど大きいのでつけやすい。
いよいよLEDの取り付け、極性があるので「長い方がA」と呪文のように唱えなら刺していった。
電解コンデンサも「長い方がプラス」と間違いないように。
一番難易度の高かったスライドスイッチ、足が短いので端からハンダ付けして固定を確認してから
中央の3本をハンダ付けした。
次は最初に間違ったクロックムーブメント部分、ここは完成品なのでそのままつけてるだけ。
基板側に数字が書いてあってどこへ配線するか分かりやすい。
線が硬めなのでテープで止めてハンダ付けした。
下に敷いてる耐熱パッドに粘着テープが付かないので固定できず。
クロックムーブメントのハンダ付け完了。
電池ボックスも配線、先にハンダメッキしてあるので簡単だけど、量が多いとその分熱が伝わるのも
遅くてハンダごての温度をあげてしまった。
電池ボックスの台座になるパーツを取り付け。
こんな感じで足にもなる。
両面テープでつけて完成、順番間違ってるので実際の作業はこのあと細かいパーツの取り付けをした。
電池をいれて動作確認、いきなりメロディーと共にLEDが様々なパターンで点灯。
ミスもなかったようで完璧に動作した。
超ローテク電子工作時計と超ハイテクEcho Spotを並べて撮影。
ちょっとした事だけど、これでも自信が付くのでそのうちデコーダなどもチャレンジする予定。
DSair2 Soldering Example by Yaasan
DSair2 Soldering Example by Yaasan